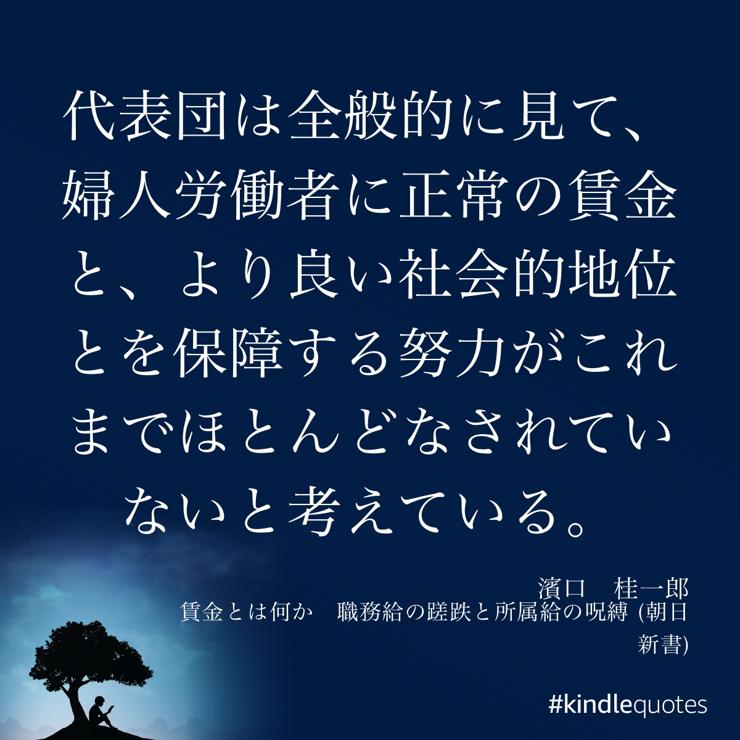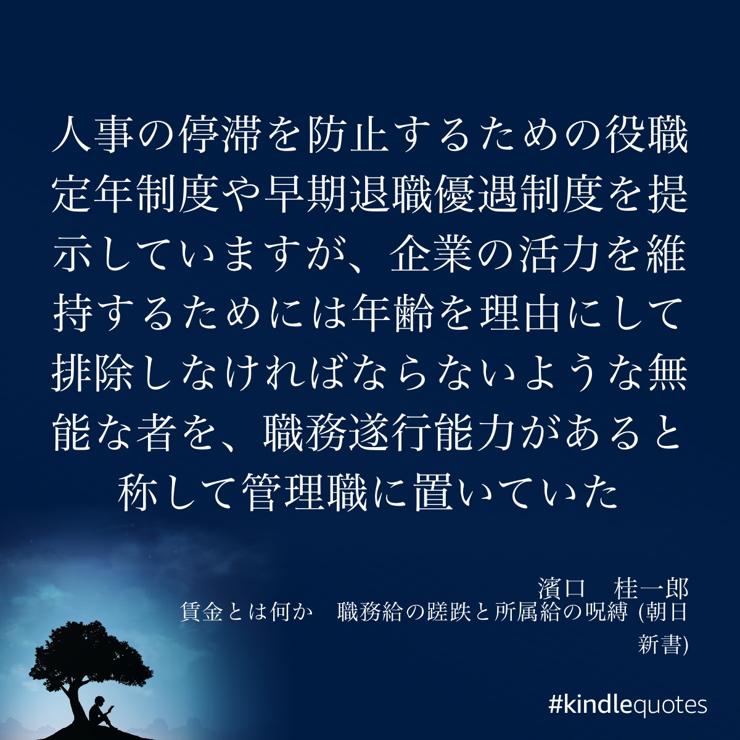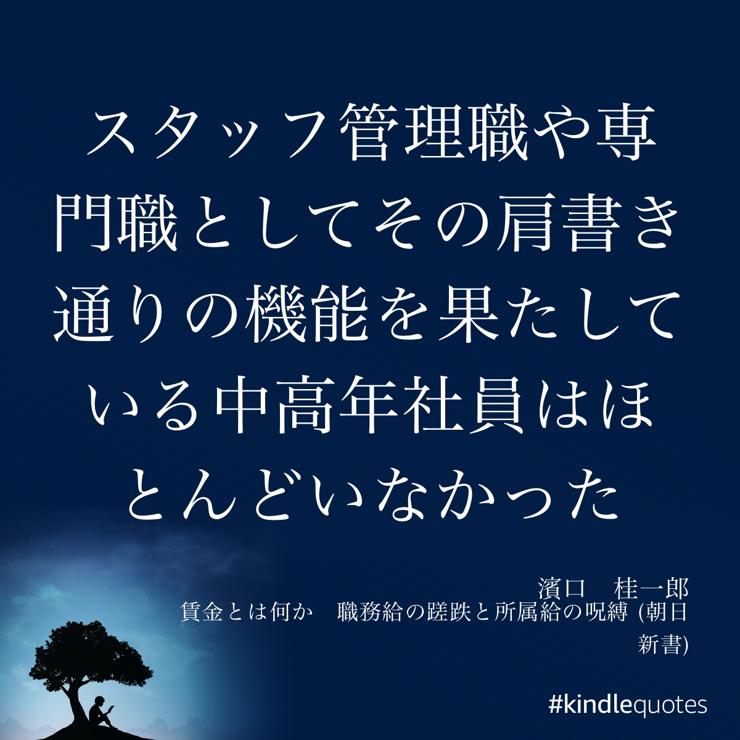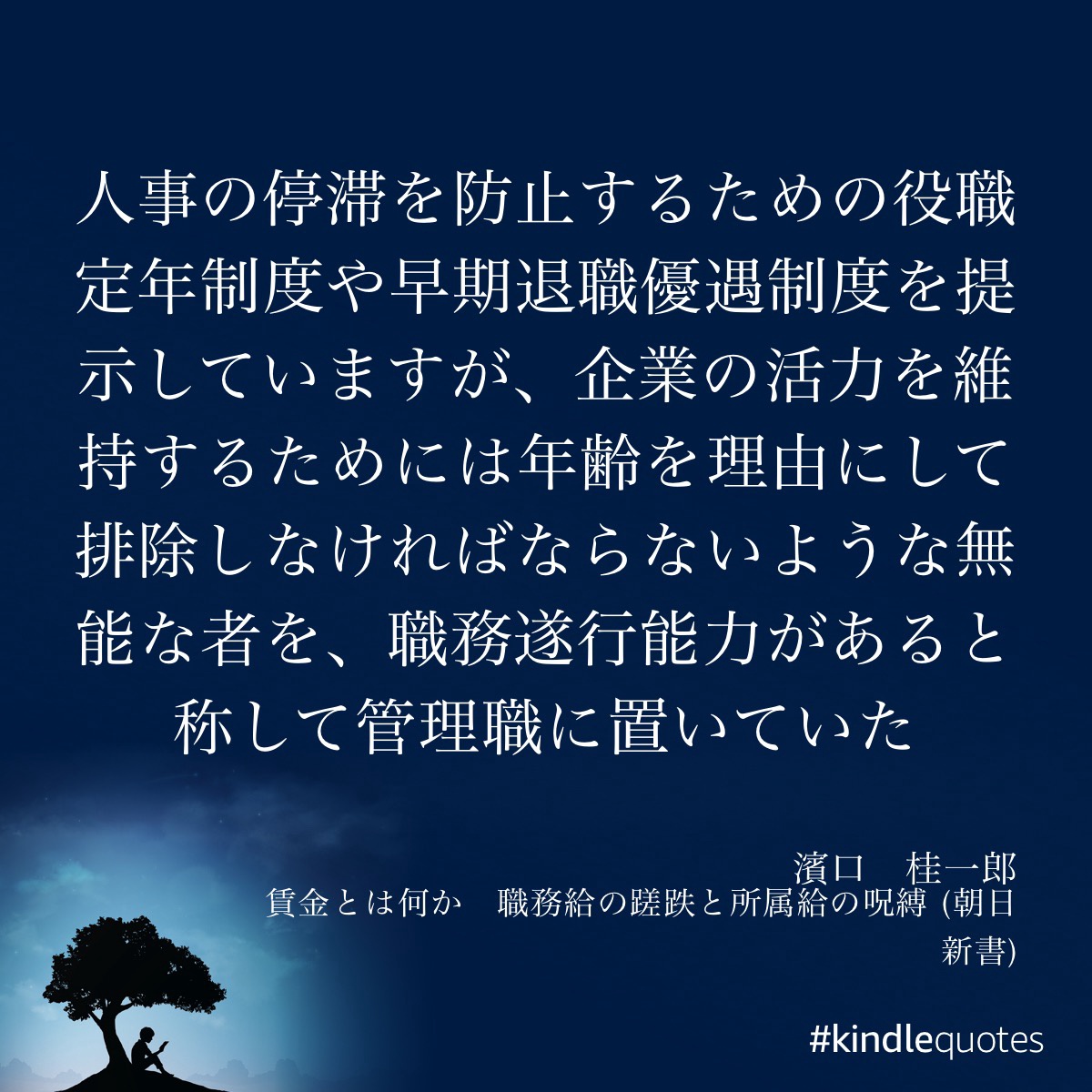濱口桂一郎さんの『賃金とは何か』を読んだ
日本では会社ごとの賃金があり、そしておおまかには在籍年数に応じて役職定年までは毎年昇給していく、という給与システムはごくあたり前のこととして受容されている(と思う)が、そうしたシステムはどのように作られてきたか、ということを労働行政の賃金マフィアとでも言うべき一群の人達の視点を中心に書いている歴史書。
「どのように」みたいな話は本に書かれているので、読んで頂ければいいとして、この本の白眉と言える部分は以下の3箇所だと思っている。
代表団は全般的に見て、婦人労働者に正常の賃金と、より良い社会的地位とを保障する努力がこれまでほとんどなされていないと考えている。
人事の停滞を防止するための役職定年制度や早期退職優遇制度を提示していますが、 企業の活力を維持するためには年齢を理由にして 排除しなければならないような無能な者を、 職務遂行能力があると称して管理職に置いていた
スタッフ管理職や専門職としてその肩書き通りの機能を果たしている中高年社員はほとんどいなかった
それぞれどのようなコンテキストであらわれた話なのかは本を読んでほしいのだが、ようするに、日本の賃金制度というのは、生活保障を暗黙の理由として、男性若年層および女性に出し渋る一方で、無能な中高年男性に過剰な賃金を与えるシステムになっていたといえるのではなかろうか。
そして、就業を開始した時点ではなんらのスキルもなく、ジョブローテーションで一つの職務を極めることもない男性労働者にたいして、高い賃金を与える合理性は(すくなくともミクロな企業経営という意味では)あまりないのだろうが、この非合理の理論的根拠となっていたのが、小池和夫の知的熟練論だった、ということになるのであろう。
フィクションにもとづいて男性に不当に高い賃金を与え続けることにより、豊かな国内市場が誕生し、輸出と消費の両輪により実際にかなり豊かな消費社会を手にいれることに我々は成功した、とも言えるわけでいってみれば合成の誤謬の反対だ。みんなが間違った結果全体としては正解を引いている、というような。
あるいは別の言いかたをすれば賃金の世界というのは徹頭徹尾男性の世界になっていて、女性はここから完全に排除されていたのだが、21世紀にはいって男女同一労働同一賃金が問題となりはじめると、女性も男性と同様のジョブローテーション、定期昇給のコースに乗ることができるようになった、という形で課題が「解決」されることとなった。
冷静に考えてみると出産前後で男性と比較して長期間就労から離脱する女性にとって、こうした処遇はあいかわらず非常に差別的なままなのであるが、かといってスキルと職務にたいして値段をつけるような賃金制度に移行すれば「専門職としてその肩書き通りの機能を果たしている中高年社員はほとんどいな」い以上多くの労働者が最低賃金で労働することとなり、国内消費市場は崩壊し労働者、資本家双方が大損をすることになるのは目に見えている。
そもそも日本の女性は就労することをさほど望んではいなかったという前提はあり、このゲームに参加することはおそらく多くの女性にとって不本意なことであっただろう。でも、とにかく、男女共同参画は実際にそれなりの成果を上げつつある。こうなってしまうと男性を中心とした生活保障的な賃金制度が不合理かつ抑圧的かつ差別的なものであることはあきらかであり、なんらかの修正は確実に必要なのだろう、と思う。
ここで気になるのが、著者の濱口氏が自分のブログで書評を多数紹介しているのだが、どうもその殆どが男性によって書かれているように見えるというのがある(俺自身このままでは「スタッフ管理職や専門職としてその肩書き通りの機能を果たして」いない中年男性へといずれ遷移していくだろう)。
女性の当事者による女性を主体とした議論が盛り上がることによって日本の賃金制度はよりよいものになっていくのではないかと思うのだが(そのよりよい賃金において俺が損をする側であるというのはこの際忘れるしかない)、どうも現状結局「賃金とは男の世界」というありかたが打破されているようには思えない。こうした議論の中心になるのはやはり労働組合なのではないかと思うのだが、女性の組織率は男性に輪をかけて低い。正直なんか、あんまり期待できないところではある。
そして結局自分は「当事者」ではないし、得をしている側でもあるわけで、これ以上の関心を持てない、というのが正直なところではある。
以下は完全な与太話
日本の年功制賃金は「若い男性に金を与えれば共産化するから若いうちは貧乏にさせとけ」という発想がベースの一つにあったことが本書に記されている。このような賃金制度のもとで若い男性は「生活するだけでやっと」という賃金しか得られない、ということになった。これはつまり「大人になっても娯楽にお金を使えない」==「大人になっても子供向けの娯楽でごまかすしかない」という結果を招くことになったのではないか。日本のマンガ、アニメ産業が奇形的に発達したことの原因に「紙とペンとインクが安かった」ことを挙げる人がかなり多いと思うのだが「大人が大人向けの娯楽を楽しめるだけのお金を持っていなかった」ことも一定の寄与があったのではないかと思う。
そして、ダークナイトやMCUなどアメコミ映画がアメリカで大人にも受け入れられただとか、あるいは近年のanimeの世界的流行なども同じようなバックグラウンドがありえるのでないか。つまり欧米では「スキル」にまともな金額がつかなくなってきており(その結果が若年層のタスクワーカー化)、大人が大人の娯楽に金をつかえなくなってきている、と。コミケが完全に地球人全員のお祭になっていたのを見ながら、気温40度の東一般待機列にならびながら本書を読んだのでそんなことを思った次第。
以上完全に与太話。